 多くの企業が利益改善を目指す際、真っ先に取り組むのが「経費削減」ではないでしょうか。不要な支出を抑え、コストカットを進めることは確かに大切な要素です。しかし、本当の利益改善の近道は、実は会計の捉え方を変えることにあるのです。
多くの企業が利益改善を目指す際、真っ先に取り組むのが「経費削減」ではないでしょうか。不要な支出を抑え、コストカットを進めることは確かに大切な要素です。しかし、本当の利益改善の近道は、実は会計の捉え方を変えることにあるのです。
経費削減には限界があります。どれだけ削減しても、事業運営に必要な最低限のコストは残ります。一方で、会計視点を変えると、まったく新しい可能性が見えてきます。例えば、固定費と変動費の区分を見直すことで、損益分岐点を下げられるケースがあります。
具体的には、製造業の場合、従来は固定費として計上していた工場の維持費を、生産量に応じた変動費として再構築することで、需要変動に強い収益構造を作れます。ITサービス企業ではサブスクリプションモデルを導入し、一時的な収益認識から継続的な収益計上へと移行することで、安定した財務基盤を構築できます。
また、会計視点の変化は投資判断にも影響します。短期的なROI(投資収益率)だけでなく、顧客生涯価値(LTV)を重視することで、マーケティング予算の配分が変わり、結果的に収益性が向上するケースも少なくありません。
キャッシュフロー経営の観点も重要です。帝国データバンクの調査によれば、黒字倒産する企業の多くは会計上の利益を追求するあまり、キャッシュの流れを軽視していました。売上や利益だけでなく、現金の動きを重視した経営判断が持続可能な成長には不可欠です。
会計視点の変化は社内の意識改革にもつながります。部門ごとの採算性を明確にすることで、従業員一人ひとりがコスト意識を持ち、自発的な改善活動が生まれやすくなります。経理部門だけでなく、全社で財務リテラシーを高めることが、真の意味での利益改善につながるのです。
もちろん、経費削減も大切な要素であることに変わりはありません。しかし、「削る」だけの思考から、「創造的に組み替える」思考へと転換することで、持続可能な利益体質を構築できます。
会計は単なる記録ではなく、経営の羅針盤です。その見方を変えることで、これまで気づかなかった改善ポイントが見えてくるでしょう。利益改善に悩む経営者の皆様は、まず会計の捉え方から見直してみてはいかがでしょうか。


 会社でも家庭でも、お金が残るかどうかは「収入-支出」という単純な構造に支配されています。しかし多くの方がこの基本を見失い、気づけばお金が残らない状況に陥ってしまいます。今日は会計の基礎知識から、真の利益構造を理解し、お金が自然と残る習慣について考えてみましょう。
会社でも家庭でも、お金が残るかどうかは「収入-支出」という単純な構造に支配されています。しかし多くの方がこの基本を見失い、気づけばお金が残らない状況に陥ってしまいます。今日は会計の基礎知識から、真の利益構造を理解し、お金が自然と残る習慣について考えてみましょう。
 「貯金ができない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。毎月給料は入ってくるのに、いつの間にか使い切ってしまう。この悪循環から抜け出すためには、発想の転換が必要です。今回は「プロフィットファースト」という考え方を取り入れて、会社経営と個人の家計、両方で実践できる貯金体質になる方法をご紹介します。
「貯金ができない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。毎月給料は入ってくるのに、いつの間にか使い切ってしまう。この悪循環から抜け出すためには、発想の転換が必要です。今回は「プロフィットファースト」という考え方を取り入れて、会社経営と個人の家計、両方で実践できる貯金体質になる方法をご紹介します。
 企業経営において最も重要な要素の一つが「キャッシュフロー管理」です。売上が好調でも資金繰りに失敗して倒産する企業は少なくありません。では、お金が残る会社と残らない会社には、どのような違いがあるのでしょうか。
企業経営において最も重要な要素の一つが「キャッシュフロー管理」です。売上が好調でも資金繰りに失敗して倒産する企業は少なくありません。では、お金が残る会社と残らない会社には、どのような違いがあるのでしょうか。
 多くの中小企業が直面する課題の一つに、売上は伸びているのに利益が思うように増えないという悩みがあります。実際、日本の中小企業の約7割が恒常的な利益率の低さに苦しんでいるというデータもあります。しかし、そんな中でも粗利率の改善によって大きく業績を伸ばした企業が存在します。
多くの中小企業が直面する課題の一つに、売上は伸びているのに利益が思うように増えないという悩みがあります。実際、日本の中小企業の約7割が恒常的な利益率の低さに苦しんでいるというデータもあります。しかし、そんな中でも粗利率の改善によって大きく業績を伸ばした企業が存在します。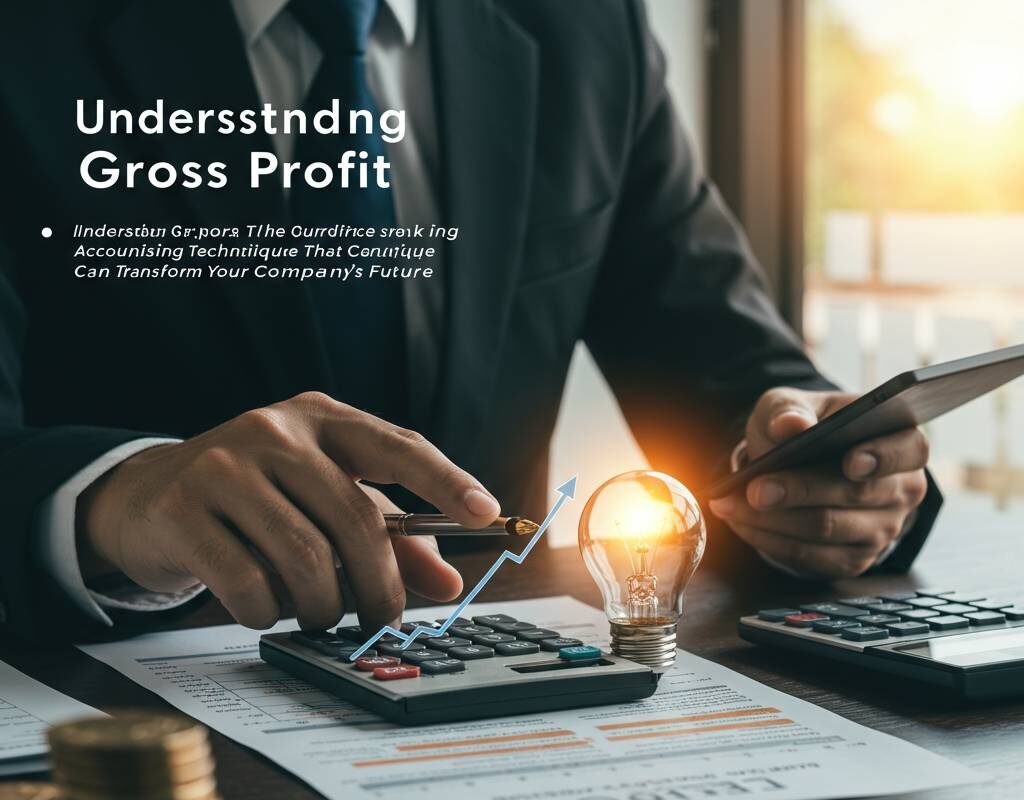
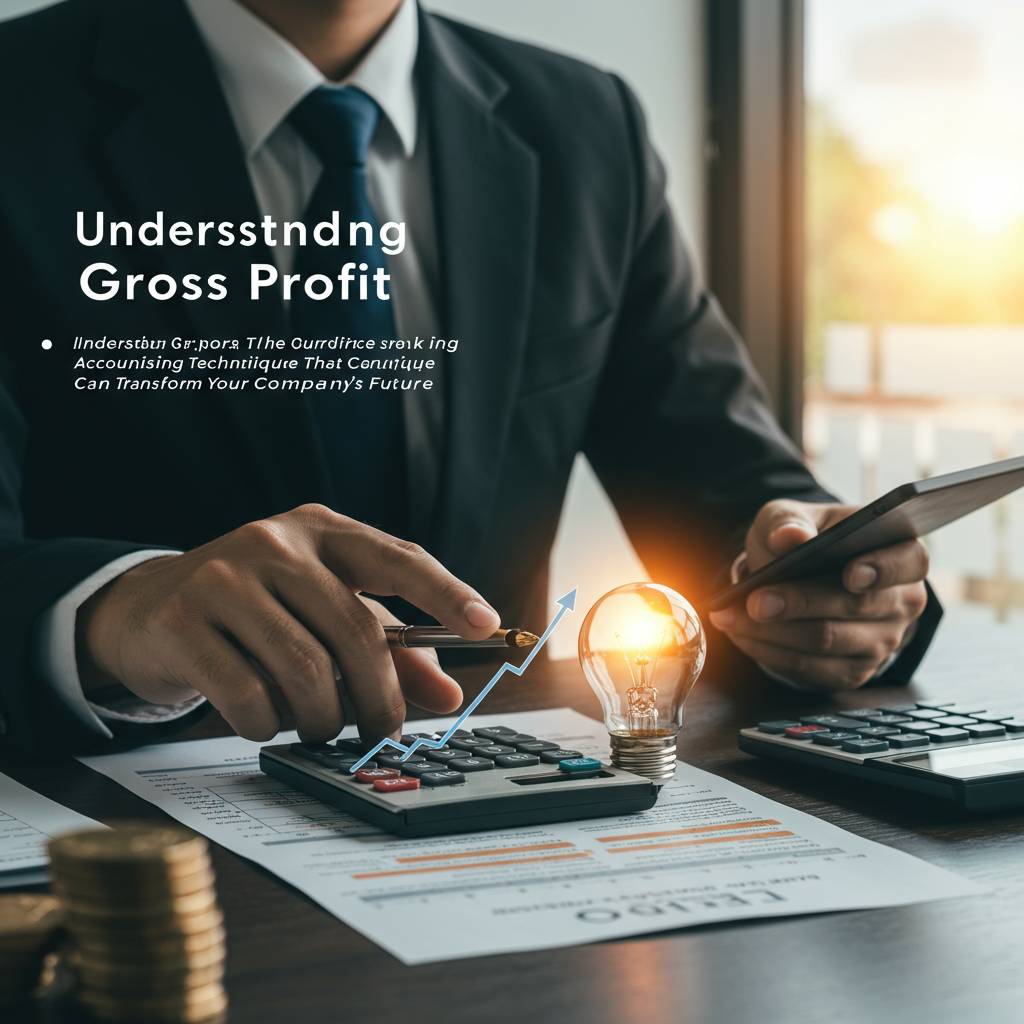 「売上総利益」という言葉を聞いたとき、皆さまはどのようなイメージを持たれるでしょうか。単なる会計用語の一つと思われるかもしれませんが、実はこの数字こそが、企業の健全性や成長性を測る重要な指標なのです。
「売上総利益」という言葉を聞いたとき、皆さまはどのようなイメージを持たれるでしょうか。単なる会計用語の一つと思われるかもしれませんが、実はこの数字こそが、企業の健全性や成長性を測る重要な指標なのです。
 「売上は好調なのに、なぜかお金が残らない」というお悩みをお持ちの方は少なくありません。この状況を根本から変えるのが「プロフィットファースト」という考え方です。従来の「売上−経費=利益」という計算式を「売上−利益=経費」と逆転させる発想法です。
「売上は好調なのに、なぜかお金が残らない」というお悩みをお持ちの方は少なくありません。この状況を根本から変えるのが「プロフィットファースト」という考え方です。従来の「売上−経費=利益」という計算式を「売上−利益=経費」と逆転させる発想法です。
 経営者の皆様は「粗利」をどれだけ意識されていますか?売上至上主義から脱却し、真の経営力を高めるためには粗利こそが重要な指標となります。
経営者の皆様は「粗利」をどれだけ意識されていますか?売上至上主義から脱却し、真の経営力を高めるためには粗利こそが重要な指標となります。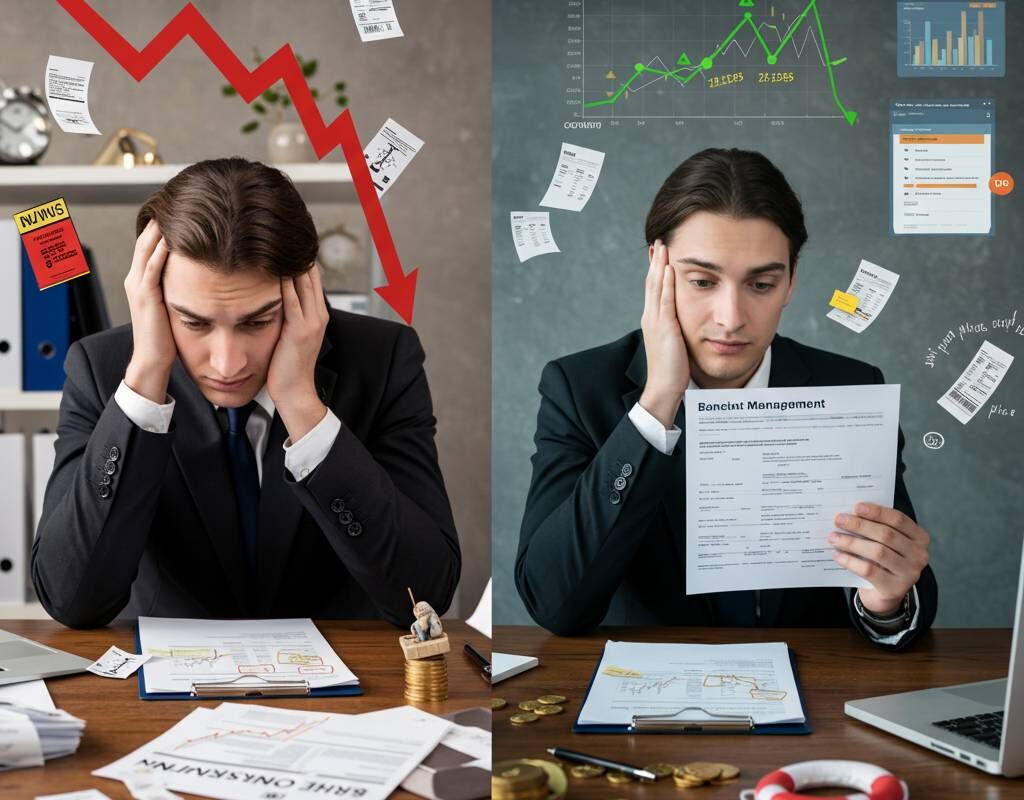
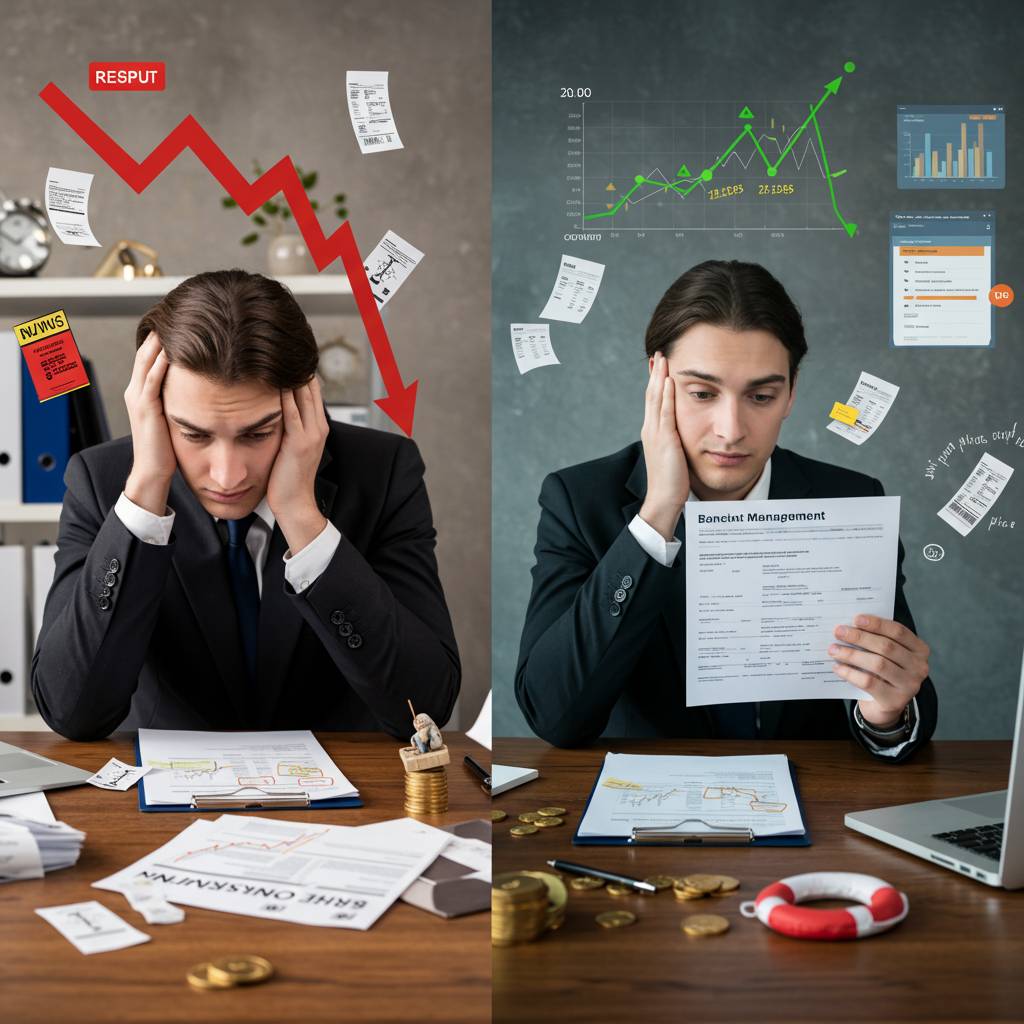 経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。
経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。
 ビジネスを成功させる上で最も重要な要素の一つが「売上総利益」です。この数字を最大化することができれば、企業の健全な成長と安定した経営基盤の構築が可能になります。しかし、多くの企業経営者や財務担当者が「原価削減」と「適切な価格設定」のバランスに悩んでいるのが現状です。
ビジネスを成功させる上で最も重要な要素の一つが「売上総利益」です。この数字を最大化することができれば、企業の健全な成長と安定した経営基盤の構築が可能になります。しかし、多くの企業経営者や財務担当者が「原価削減」と「適切な価格設定」のバランスに悩んでいるのが現状です。