 会社経営において「売上は順調なのに、なぜかお金が残らない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。実はこれは経営の構造的な問題であり、プロフィットファーストという考え方を取り入れることで解決できる可能性があります。
会社経営において「売上は順調なのに、なぜかお金が残らない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。実はこれは経営の構造的な問題であり、プロフィットファーストという考え方を取り入れることで解決できる可能性があります。
プロフィットファーストとは、マイク・ミカロウィッツが提唱した経営手法で、従来の「売上−経費=利益」という公式を「売上−利益=経費」と捉え直す考え方です。つまり、まず最初に利益を確保してから残りを経費に充てるという発想の転換です。
この手法の実践には、複数の銀行口座を活用することがポイントとなります。売上が入金される主口座から、一定割合を「税金口座」「利益口座」「経営者報酬口座」などに自動的に振り分けるシステムを構築します。こうすることで、手元に残った資金内でのみ経費を使うという規律が生まれます。
例えば売上100万円の場合、最初に5%を利益として5万円を別口座に移します。10%を税金用に10万円、10%を経営者報酬として10万円を確保します。残りの75万円で経費をやりくりするという考え方です。
このアプローチが優れている点は、心理的なハードルを下げることにあります。人間は目の前にあるお金を使わずにいることが難しいものです。しかし、最初に別口座に移してしまえば、使える予算は明確になり、無駄な支出を自然と抑制できます。
特に中小企業や個人事業主にとって効果的なのは、「現金主義」で経営判断をすることです。会計上の利益ではなく、実際に手元にあるキャッシュで判断することで、資金ショートのリスクを大幅に減らせます。
製造業のA社では、売上は年々増加していたものの、常に資金繰りに苦しんでいました。プロフィットファーストを導入して半年後、初めて余裕資金が生まれ、新規設備投資も可能になりました。
もちろん、この方法にも注意点があります。急な大型投資や季節変動の大きいビジネスでは、柔軟な調整が必要です。また、極端なコスト削減は品質低下を招く恐れもあるため、バランス感覚が重要です。
会社経営において最も重要なのは継続性です。一時的に利益を出すのではなく、安定してキャッシュを生み出す仕組みを作ることが、長期的な成功につながります。プロフィットファーストはその実現のための有効な手段と言えるでしょう。


 企業経営において「売上」だけを追いかける時代は終わりました。現在の経営者に求められているのは、「粗利」を意識した会計管理です。特に中小企業においては、限られたリソースを効率的に活用するために、粗利を重視した経営判断が成長の鍵を握っています。
企業経営において「売上」だけを追いかける時代は終わりました。現在の経営者に求められているのは、「粗利」を意識した会計管理です。特に中小企業においては、限られたリソースを効率的に活用するために、粗利を重視した経営判断が成長の鍵を握っています。
 多くの企業経営者が「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みを抱えています。実はこの問題、粗利を適切に管理することで大きく改善できるのです。今回は粗利を意識することで財務体質が劇的に改善した企業の事例をご紹介します。
多くの企業経営者が「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みを抱えています。実はこの問題、粗利を適切に管理することで大きく改善できるのです。今回は粗利を意識することで財務体質が劇的に改善した企業の事例をご紹介します。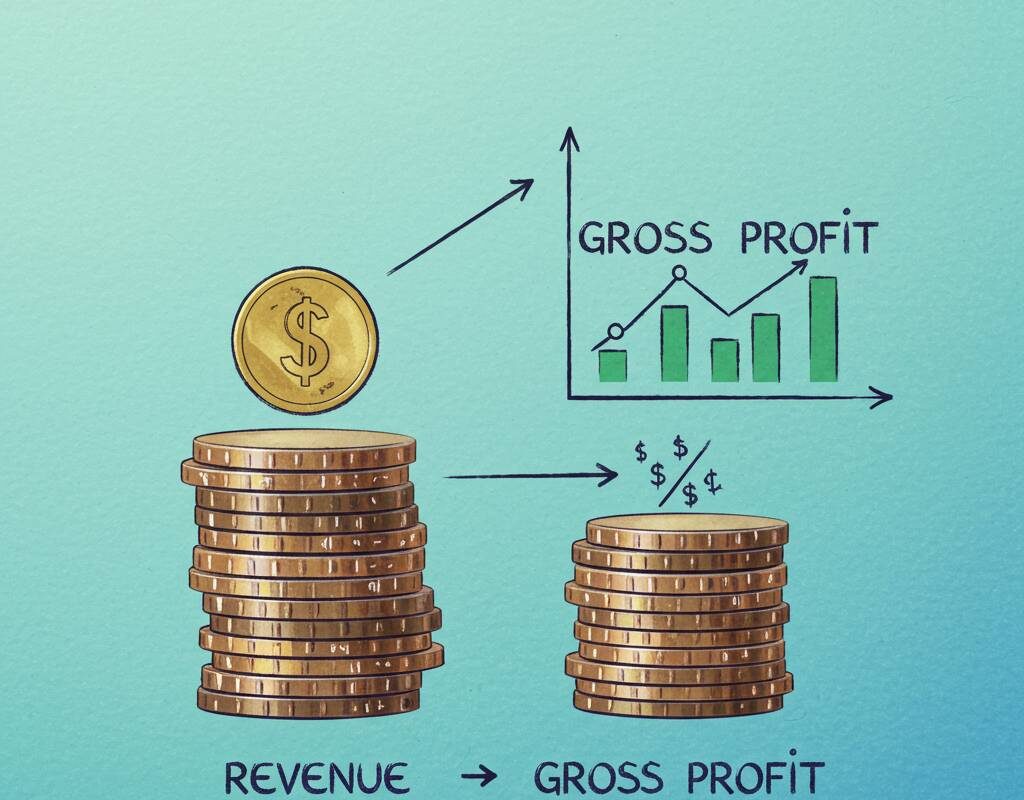
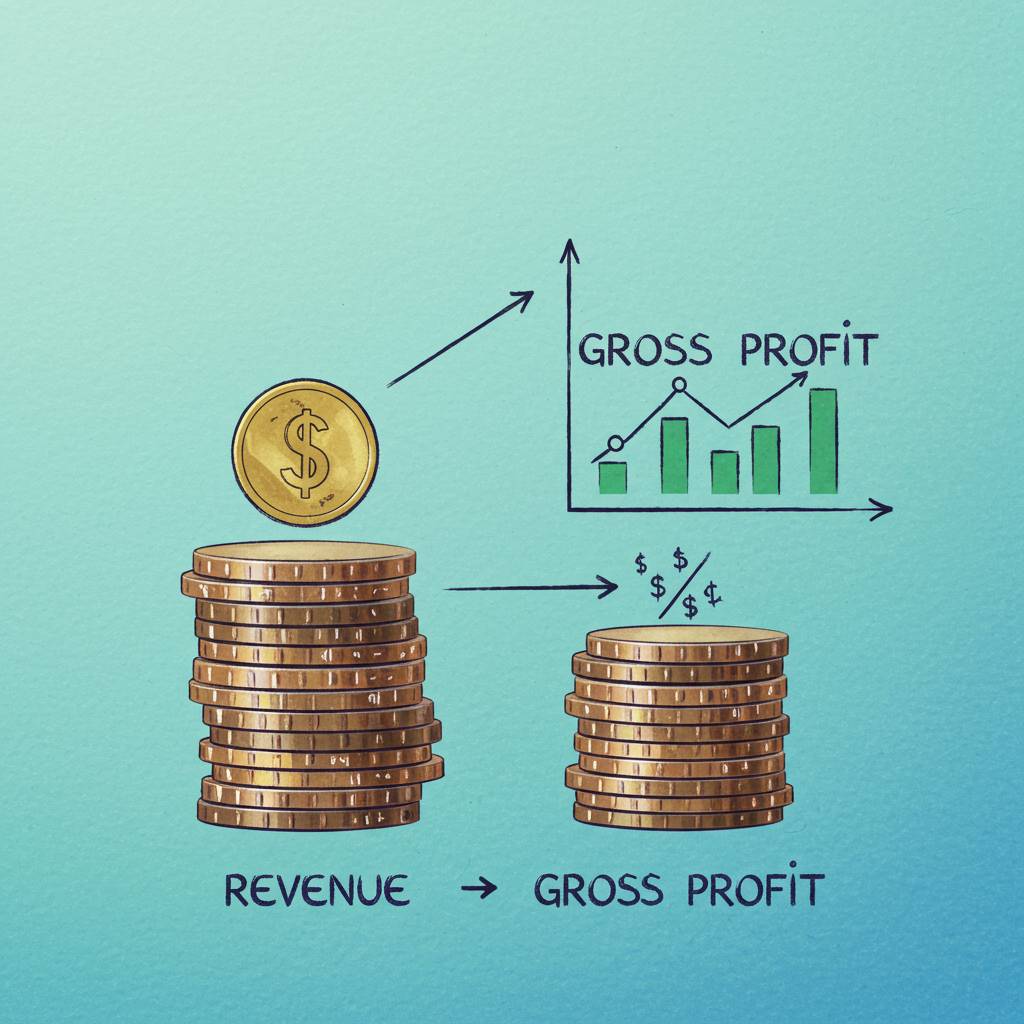 経営者や事業主の皆さま、ビジネスの成功を測る指標として何を重視していますか?多くの方が「売上高」を第一に考えがちですが、実はそれだけでは企業の真の健全性を測ることはできません。今日は「売上」ではなく「粗利」に注目することの重要性についてお話しします。
経営者や事業主の皆さま、ビジネスの成功を測る指標として何を重視していますか?多くの方が「売上高」を第一に考えがちですが、実はそれだけでは企業の真の健全性を測ることはできません。今日は「売上」ではなく「粗利」に注目することの重要性についてお話しします。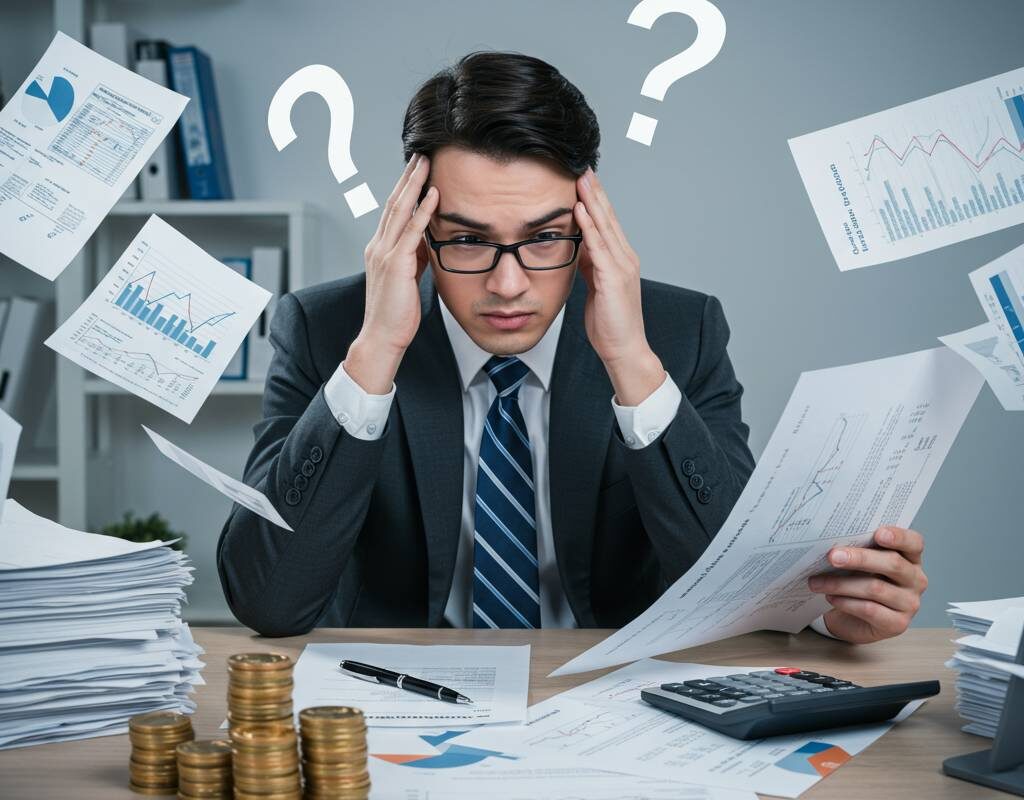
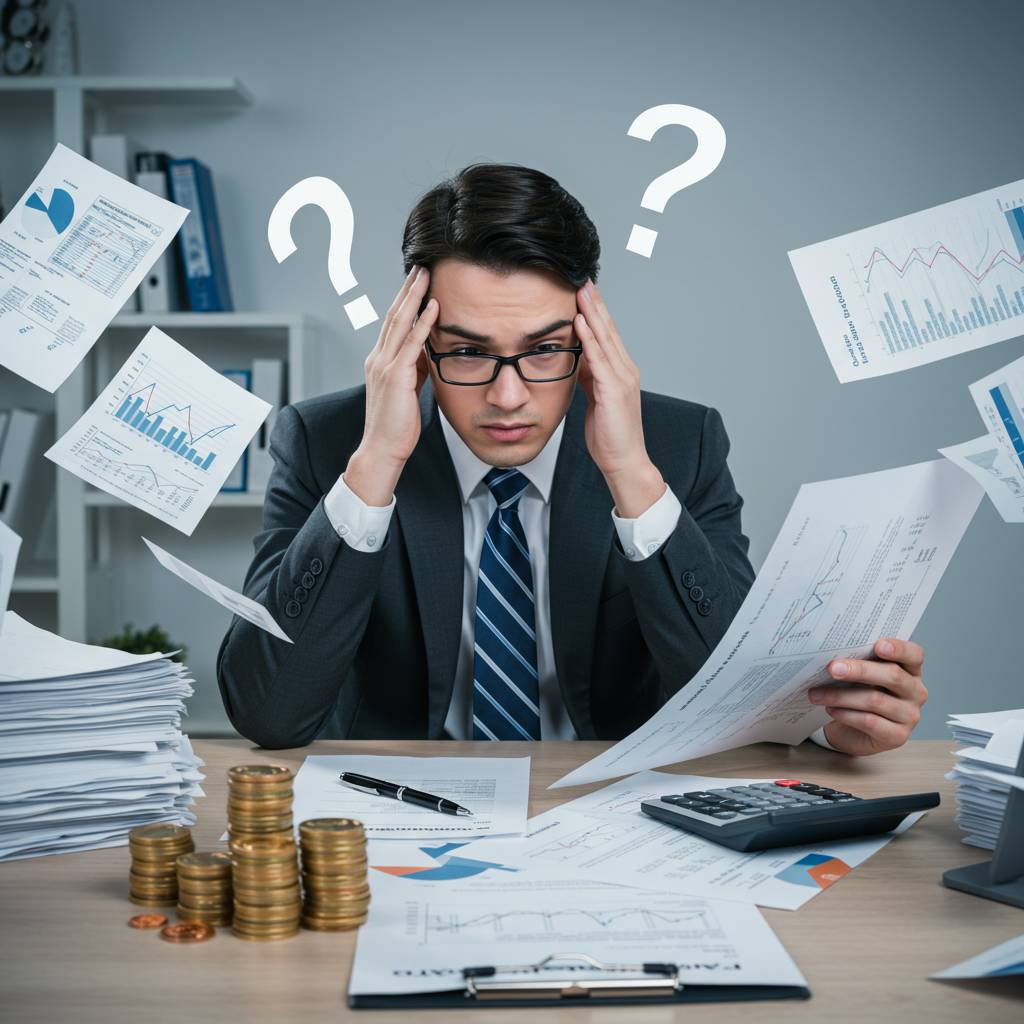 経営者として日々奮闘されている皆様、「売上は上がっているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みはありませんか?実はこの問題、会計の基本原則を理解していないことが原因かもしれません。今回は、財務体質を強化し、真の利益を生み出すために知っておくべき会計の基本原則7つをご紹介します。
経営者として日々奮闘されている皆様、「売上は上がっているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みはありませんか?実はこの問題、会計の基本原則を理解していないことが原因かもしれません。今回は、財務体質を強化し、真の利益を生み出すために知っておくべき会計の基本原則7つをご紹介します。
 中小企業の経営において最も重要な課題の一つが資金繰りです。特に年商1億円規模の企業では、売上は確保できていても、適切な利益が出ていないケースが少なくありません。その原因として最も多いのが「粗利率の低さ」です。
中小企業の経営において最も重要な課題の一つが資金繰りです。特に年商1億円規模の企業では、売上は確保できていても、適切な利益が出ていないケースが少なくありません。その原因として最も多いのが「粗利率の低さ」です。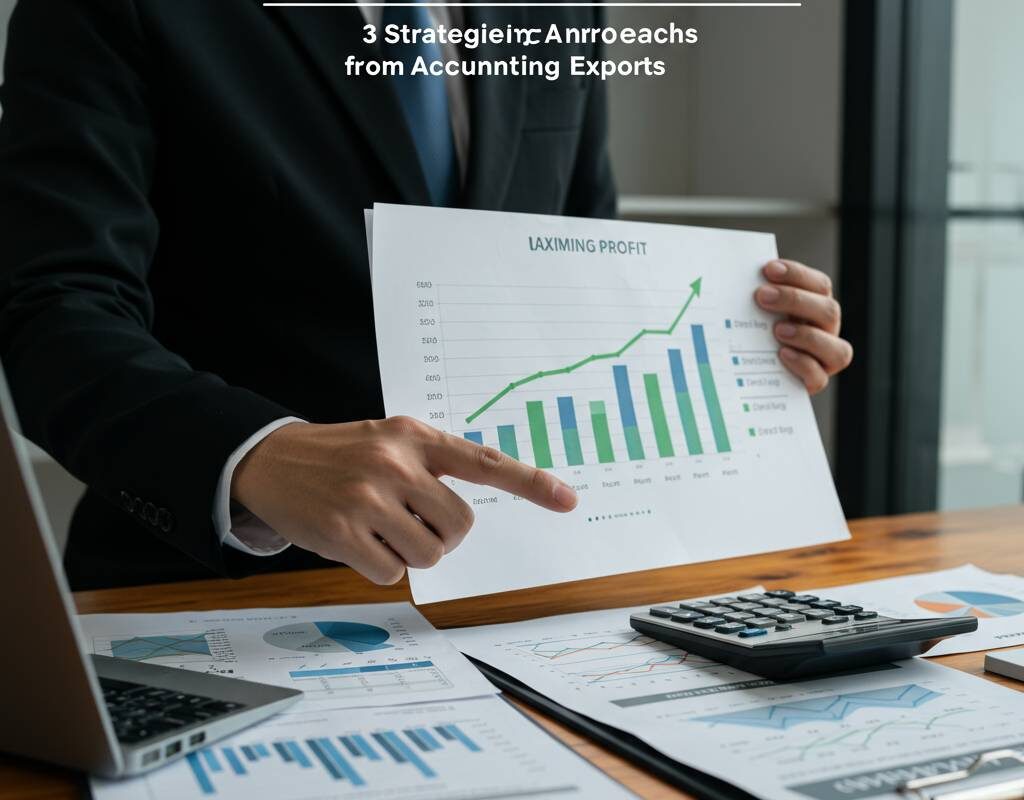
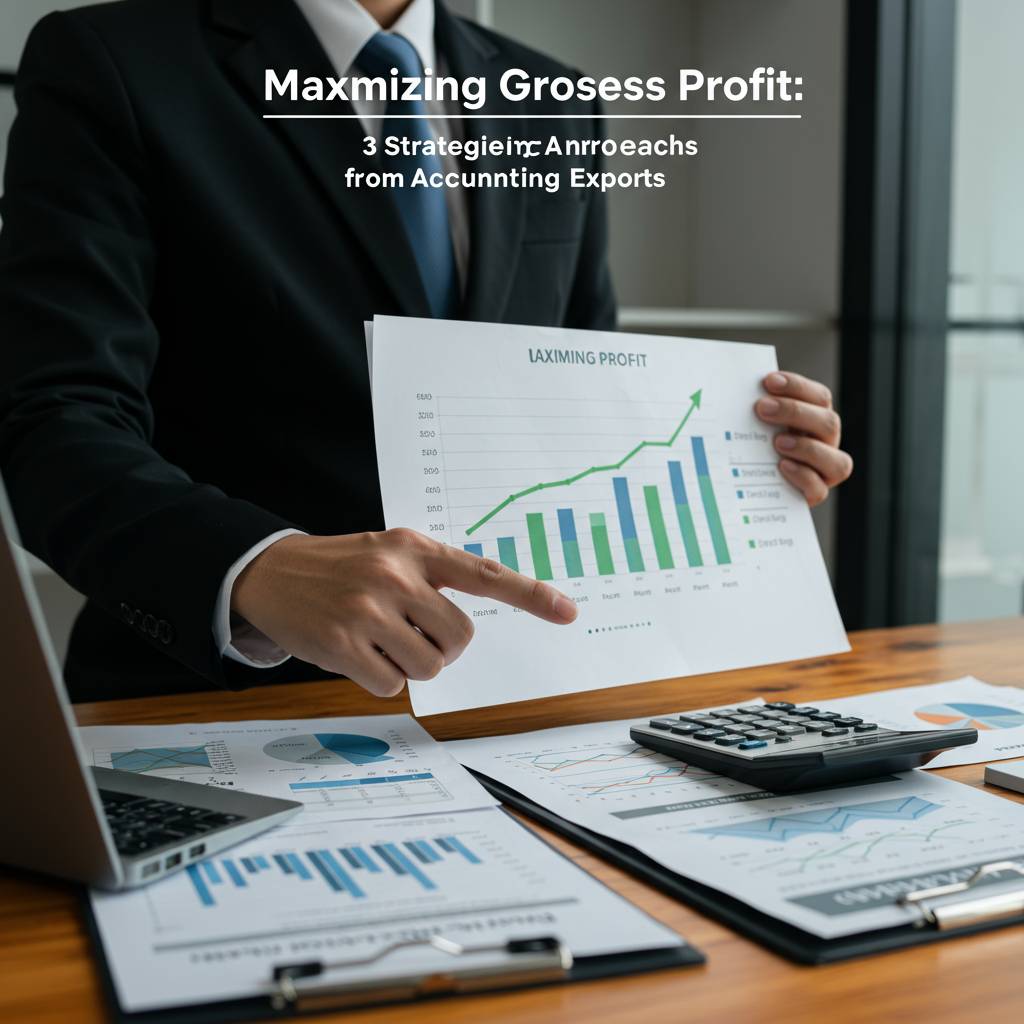 ビジネスを成長させる上で、売上総利益(粗利益)の最大化は避けて通れない重要課題です。単に売上を伸ばすだけでなく、コストと利益のバランスを最適化することが持続可能な経営の鍵となります。
ビジネスを成長させる上で、売上総利益(粗利益)の最大化は避けて通れない重要課題です。単に売上を伸ばすだけでなく、コストと利益のバランスを最適化することが持続可能な経営の鍵となります。
 多くの中小企業経営者は日々の業務に追われ、会計処理を「必要な手続き」程度にしか考えていないことがあります。しかし、適切な会計処理は単なる法的義務ではなく、企業の存続と成長に直結する重要な経営ツールなのです。
多くの中小企業経営者は日々の業務に追われ、会計処理を「必要な手続き」程度にしか考えていないことがあります。しかし、適切な会計処理は単なる法的義務ではなく、企業の存続と成長に直結する重要な経営ツールなのです。
 私のクライアントが記帳代行サービスを導入したのは、時間的余裕を作りたいという一心からでした。毎月の請求書整理や仕訳入力に費やす時間が、新規顧客との打ち合わせや商品開発の時間を圧迫していたのです。
私のクライアントが記帳代行サービスを導入したのは、時間的余裕を作りたいという一心からでした。毎月の請求書整理や仕訳入力に費やす時間が、新規顧客との打ち合わせや商品開発の時間を圧迫していたのです。
 ビジネスを成功させる鍵は、単に売上を伸ばすことだけではありません。今日のビジネス環境において重要なのは、いかに効率的に利益を生み出す構造を作るかということです。本記事では、粗利と売上総利益の概念から、持続可能な次世代型ビジネスモデルの構築方法について解説します。
ビジネスを成功させる鍵は、単に売上を伸ばすことだけではありません。今日のビジネス環境において重要なのは、いかに効率的に利益を生み出す構造を作るかということです。本記事では、粗利と売上総利益の概念から、持続可能な次世代型ビジネスモデルの構築方法について解説します。