 企業経営において最も重要な要素のひとつが「キャッシュフロー管理」です。売上を伸ばすことばかりに目が行きがちですが、実際にお金が残る仕組みを作ることこそが事業継続の鍵となります。
企業経営において最も重要な要素のひとつが「キャッシュフロー管理」です。売上を伸ばすことばかりに目が行きがちですが、実際にお金が残る仕組みを作ることこそが事業継続の鍵となります。
まず見直したいのが固定費の最適化です。事務所の家賃や人件費、システム利用料など毎月確実に出ていくお金を精査しましょう。例えば、リモートワークの導入によりオフィススペースを縮小したり、業務のデジタル化で人的コストを削減したりする方法があります。固定費を10%削減できれば、それは直接利益に反映されます。
次に重要なのが在庫管理です。過剰在庫は資金の滞留を意味します。「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ」という考え方を徹底することで、在庫に眠る資金を解放できます。アマゾンやユニクロなどの成功企業は、徹底した在庫管理によってキャッシュの流動性を高めています。
また、売掛金回収の効率化も見逃せません。請求サイクルを短くしたり、早期支払いへの割引制度を導入したりすることで、資金回収を早められます。反対に、支払いサイクルは可能な範囲で延長することで、手元資金を確保できます。
投資判断においては「ROI(投資収益率)」を重視しましょう。新規設備や事業拡大には必ず投資回収計画を立て、数値で効果を測定することが重要です。感覚や勢いだけで投資判断をすると、資金ショートのリスクが高まります。
税務戦略も忘れてはなりません。適切な経費計上や減価償却、各種控除制度の活用により、法人税などの負担を適正化できます。ただし、無理な節税策は税務調査のリスクを高めるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
最後に強調したいのが経営指標の定期チェックです。「売上総利益率」「営業利益率」「流動比率」「手元現金」などの数値を月次で確認する習慣をつけましょう。数字の変化に早く気づくことで、問題が大きくなる前に対処できます。
お金が残る経営とは、単なる節約術ではなく、ビジネス全体の仕組みを最適化する取り組みです。短期的な利益よりも長期的なキャッシュフローの安定を重視する視点が、持続可能な事業経営には欠かせません。


 多くの企業が直面する課題として「利益が出ているのに現金が残らない」という状況があります。決算書上では黒字なのに、なぜか資金繰りに苦しむ——この矛盾を解消するには、適切な会計マネジメントが不可欠です。
多くの企業が直面する課題として「利益が出ているのに現金が残らない」という状況があります。決算書上では黒字なのに、なぜか資金繰りに苦しむ——この矛盾を解消するには、適切な会計マネジメントが不可欠です。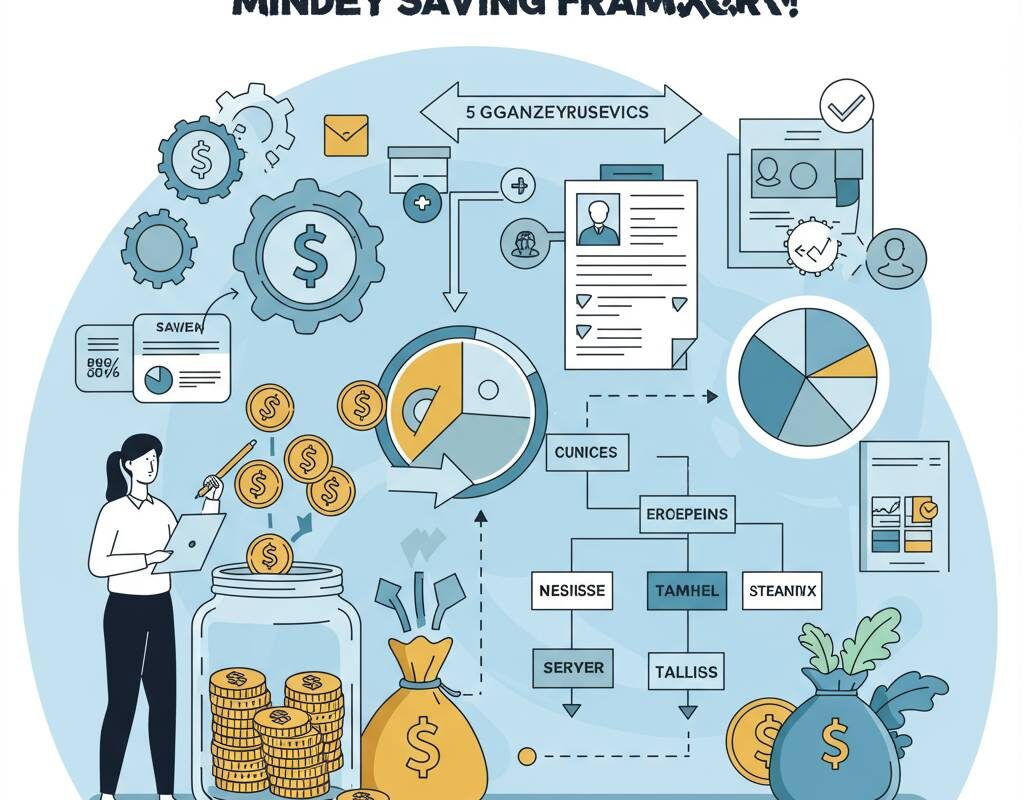
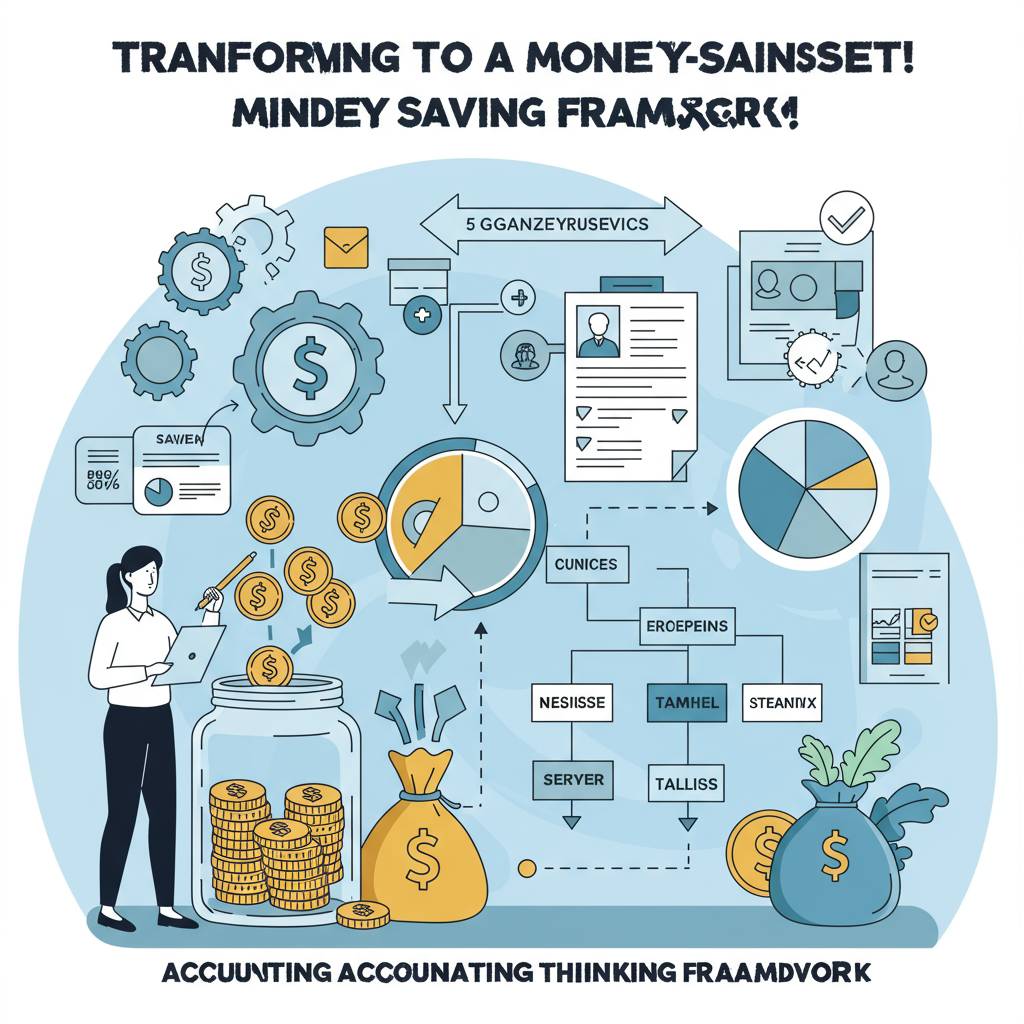 「なぜか毎月お金が残らない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。収入はそれなりにあるのに、気づけば財布の中は寂しい状態になっていませんか?実はこれ、お金との付き合い方のフレームワークができていないことが原因かもしれません。
「なぜか毎月お金が残らない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。収入はそれなりにあるのに、気づけば財布の中は寂しい状態になっていませんか?実はこれ、お金との付き合い方のフレームワークができていないことが原因かもしれません。
 企業経営において「売上総利益」は経営の健全性を示す重要な指標です。多くの経営者が売上高に注目しがちですが、真の経営力は売上総利益にこそ現れます。売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いた金額であり、いわゆる「粗利」と呼ばれるものです。この数値が高ければ高いほど、事業の基本的な収益力が強いことを意味します。
企業経営において「売上総利益」は経営の健全性を示す重要な指標です。多くの経営者が売上高に注目しがちですが、真の経営力は売上総利益にこそ現れます。売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いた金額であり、いわゆる「粗利」と呼ばれるものです。この数値が高ければ高いほど、事業の基本的な収益力が強いことを意味します。
 会社でも家庭でも、お金が残るかどうかは「収入-支出」という単純な構造に支配されています。しかし多くの方がこの基本を見失い、気づけばお金が残らない状況に陥ってしまいます。今日は会計の基礎知識から、真の利益構造を理解し、お金が自然と残る習慣について考えてみましょう。
会社でも家庭でも、お金が残るかどうかは「収入-支出」という単純な構造に支配されています。しかし多くの方がこの基本を見失い、気づけばお金が残らない状況に陥ってしまいます。今日は会計の基礎知識から、真の利益構造を理解し、お金が自然と残る習慣について考えてみましょう。
 家計や事業の収支管理に悩む方は多いのではないでしょうか。お金が残らない原因は、単なる収入不足ではなく、効率的な資金管理ができていないことにあります。今回は、財務の専門家が実践している「お金が自然と残る仕組み」を5つのステップでご紹介します。
家計や事業の収支管理に悩む方は多いのではないでしょうか。お金が残らない原因は、単なる収入不足ではなく、効率的な資金管理ができていないことにあります。今回は、財務の専門家が実践している「お金が自然と残る仕組み」を5つのステップでご紹介します。
 「貯金ができない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。毎月給料は入ってくるのに、いつの間にか使い切ってしまう。この悪循環から抜け出すためには、発想の転換が必要です。今回は「プロフィットファースト」という考え方を取り入れて、会社経営と個人の家計、両方で実践できる貯金体質になる方法をご紹介します。
「貯金ができない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。毎月給料は入ってくるのに、いつの間にか使い切ってしまう。この悪循環から抜け出すためには、発想の転換が必要です。今回は「プロフィットファースト」という考え方を取り入れて、会社経営と個人の家計、両方で実践できる貯金体質になる方法をご紹介します。
 企業経営において最も重要な要素の一つが「キャッシュフロー管理」です。売上が好調でも資金繰りに失敗して倒産する企業は少なくありません。では、お金が残る会社と残らない会社には、どのような違いがあるのでしょうか。
企業経営において最も重要な要素の一つが「キャッシュフロー管理」です。売上が好調でも資金繰りに失敗して倒産する企業は少なくありません。では、お金が残る会社と残らない会社には、どのような違いがあるのでしょうか。
 「売上は好調なのに、なぜかお金が残らない」というお悩みをお持ちの方は少なくありません。この状況を根本から変えるのが「プロフィットファースト」という考え方です。従来の「売上−経費=利益」という計算式を「売上−利益=経費」と逆転させる発想法です。
「売上は好調なのに、なぜかお金が残らない」というお悩みをお持ちの方は少なくありません。この状況を根本から変えるのが「プロフィットファースト」という考え方です。従来の「売上−経費=利益」という計算式を「売上−利益=経費」と逆転させる発想法です。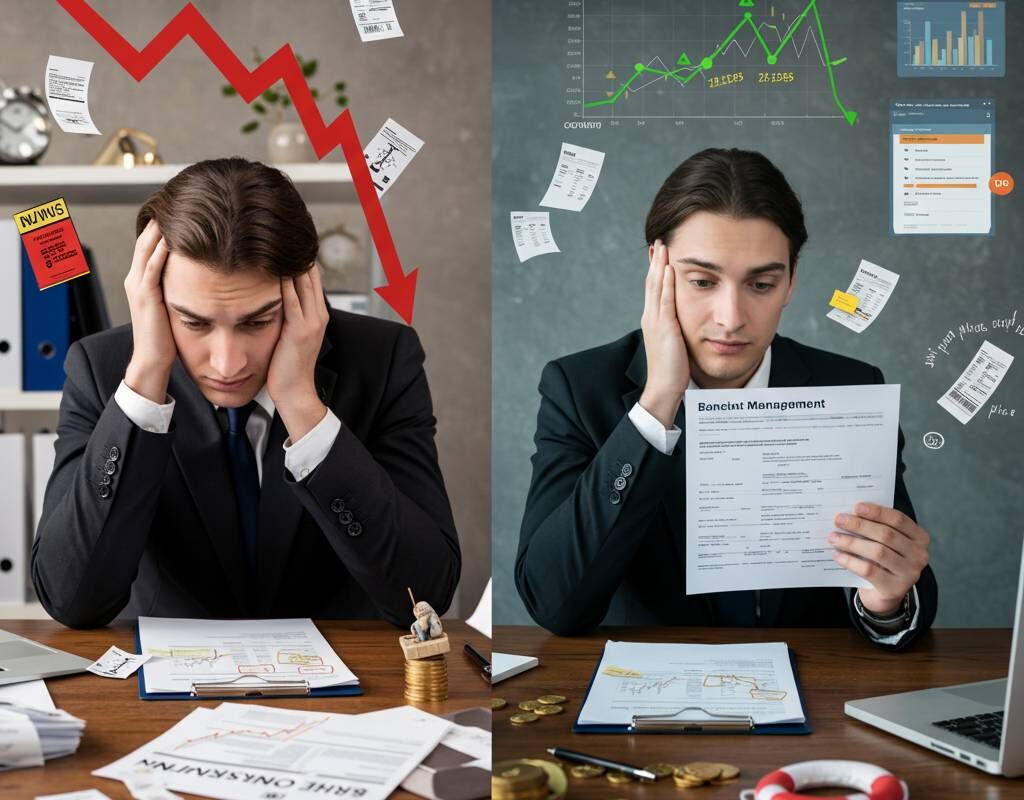
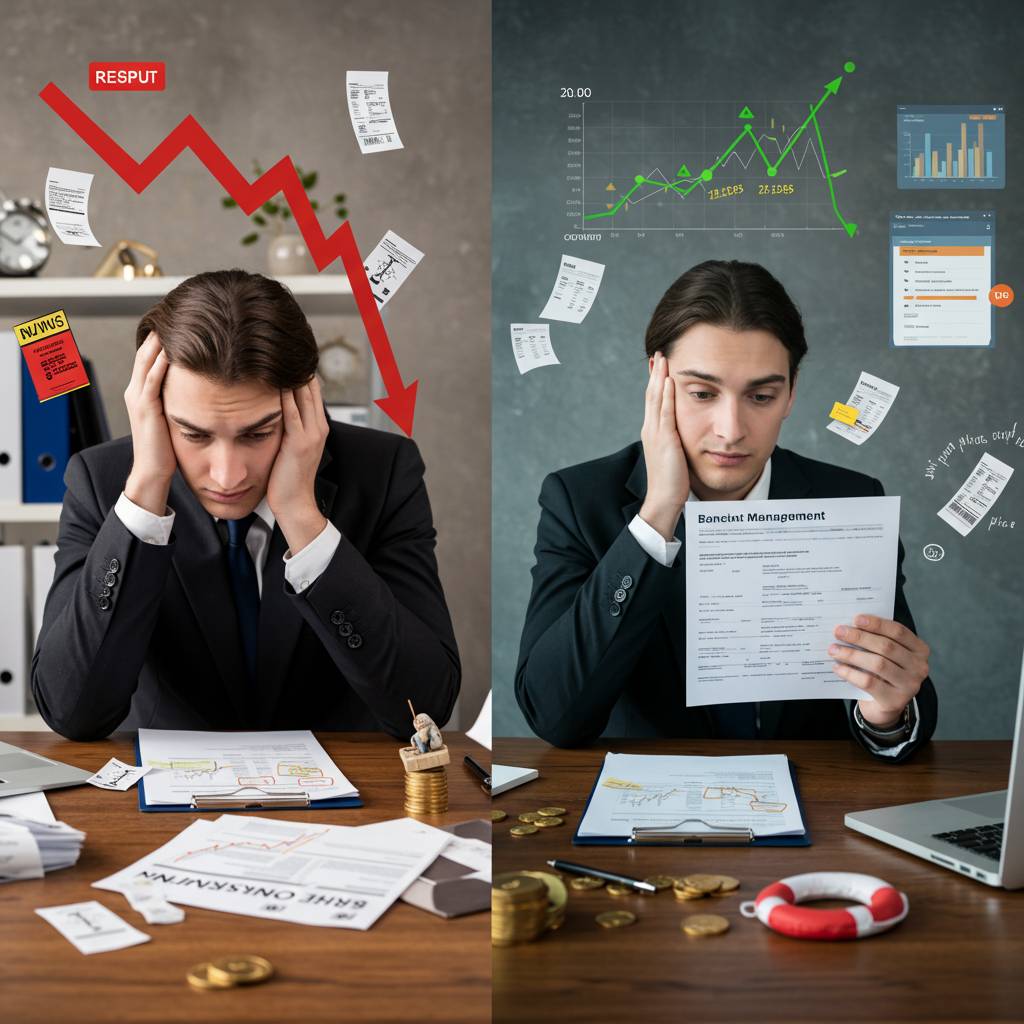 経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。
経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。